アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 佐橋雄介 弁護士 菅 隆浩 弁護士 中野常道
弁護士 嶋田祥大 弁護士 佐藤 龍 弁護士 伊藤公洋
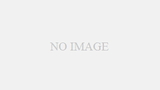
買収行動指針および公正M&A指針を踏まえた上場会社をめぐる買収事案の事例分析(上)―2024年4月~2025年3月
Ⅲ 公正M&A指針を踏まえた公正性担保措置の実施状況
1 総論
公正M&A指針(2019年6月28日公表)は、MBO[56]および従属会社買収[57]を中心に、主として手続面から、公正なM&Aのあり方を提示することを目的とする指針である。同指針は、M&Aに新たな規制を課す趣旨で提示するものではなく、公正なM&Aのあり方に関して企業社会において共有されるべきベストプラクティスとして位置づけられるべきものである(同指針2~3頁)[58]。もっとも、近時の上場会社を対象とする非公開化取引(MBO等を含み、以下「非公開化取引」という)においては、事案ごとに適切な範囲で公正M&A指針の内容を遵守することが重要な意味を持つに至っている。
すなわち、非公開化取引は、通常、買収者が、対象会社の株式に対するTOBを実施し、その後、いわゆるスクイーズアウト手続[59]を行い、対象会社の株式の全部[60]を取得することにより実行される(いわゆる二段階買収)。このような二段階買収においては、一段階目のTOBが成立した場合、対象会社の少数株主は、その後のスクイーズアウト手続により、対象会社の株主としての地位を強制的に奪われることになる。そして、スクイーズアウト手続において少数株主に対して支払われる対価(以下「スクイーズアウト対価」という)の額は、先行するTOBにおけるTOB価格[61]と、通常、同額に設定される[62]。当該スクイーズアウト対価に不満のある少数株主は、会社法上の手続に基づき、スクイーズアウト対価の額を争うことが認められている[63]。
続きを読むにはログインしてください
資料版商事法務の新規お申し込みはこちらから

